登山者情報1134号
【2008年02月16-17日/山形県山岳連盟指導員研修会in鳥海山/井上邦彦調査】
定例である山形県山岳連盟指導員会冬季研修会が鳥海山麓で行われた。八幡山岳会の池田さん達や岳人長井の青木さんが段取りをしてくれ、約30名の参加となった。今回の会場は湯の台温泉鳥海山荘である。
研修会は青木さんから日本山岳協会指導員制度の説明があった。日本山岳協会の指導員が日本体育協会公認スポーツ指導者に変わり、移行期間も残すところ1年間となったので、最後の確認作業に入ることになる。
登山技術の講師は筆者が受け持った。今回は雪崩がテーマということで、アバランチビーコンやプローブを始め、応急処置も含めた座学を実施した。その後は、何時ものとおり楽しい懇親会で夜が更けた。
翌日はまずまずの天候。鳳来山に登り、適当な所で実技指導である。始めに雪崩概論を述べ、2名が雪庇を故意に踏み抜いて落下させた。次に崩壊した斜面を綺麗にして指を刺し込み、雪層を実感する。それぞれが考えた崩壊予想箇所に印をつけて雪柱を崩壊させ、崩壊面を確認して雪層が斜めになっていることを確かめる。この雪層の傾きが雪庇に雪洞を掘る時のポイントになることを解説し、雪洞の掘り方について説明した。
下記の写真は、筆者撮影の他、池田さんから送っていただいたものを使用している。
| 初日の講習会にて |
 |
| 二日目の講習会 |
 |
| 青木さんの司会で始まりました |
 |
| 指導委員長(HZU)の挨拶 |
 |
| 早速、講習が始まりました |
 |
| 雪崩埋没者の蘇生方法 |
 |
| ビニールテープを利用した傷の被覆方法 |
 |
| 会食が始まる前に、八幡山岳会から簡易固定法が披露されました |
 |
| ビニール袋に息を吹き込むと |
 |
| もう少しかな? |
 |
| 完成しました |
 |
| それでは乾杯〜! |
 |
| 見事に並んだ銘酒の数々 |
 |
| 山形県遭難救助訓練でもお世話になりました |
 |
| 昔の話も出てきました |
 |
| 参加くださった皆さん |
| 会田さん |
船越さん |
 |
 |
| 折原さん |
國井さん |
 |
 |
| 齋藤さん |
堀さん |
 |
 |
| 細谷さん |
高橋さん |
 |
 |
| 本間さん |
阿部さん |
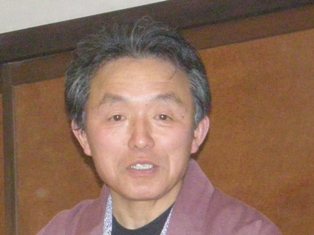 |
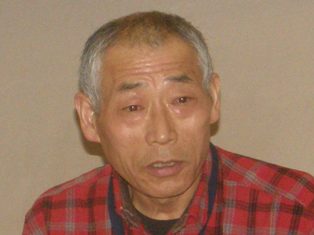 |
| 三浦さん |
伊藤さん |
 |
 |
| 青木さん |
平田さん |
 |
 |
| 須貝さん |
佐藤さん |
 |
 |
| 鈴木さん |
松田さん |
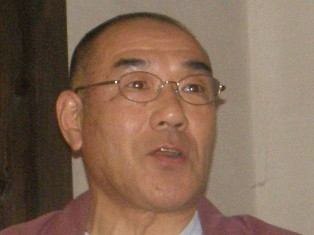 |
 |
| 辻村さん |
東海林さん |
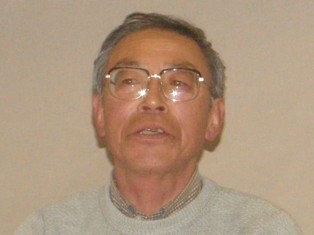 |
 |
| 菅埜さん |
平田さん |
 |
 |
| 多田さん |
工藤さん |
 |
 |
| 池田さん |
新保さん |
 |
 |
| 大滝さん |
芝田さん |
 |
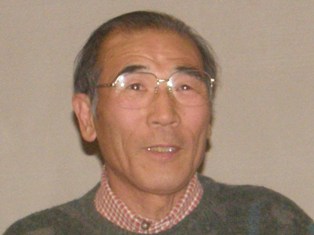 |
| 二日目は鳳莱山を目指す |
 |
| 雪は締まっており快適だ |
 |
| 堀会長が自ら先頭をあるいてくれた |
 |
| 結構な人数である |
 |
| 雑木林に入る |
 |
| ムシカリが迎えてくれた |
 |
| 徐々に登りとなる |
 |
| 眼前をウサギが駆け抜けていった |
 |
| 訓練場所に到着 |
 |
| 鳳莱山々頂を望む |
 |
| 木々に着いた雪が幻想的だ |
 |
| 雪庇もほどほどに出ている |
 |
| 始めはアバランチビーコンの確認 乾電池はオキシライドを使うとトラブルことがある |
 |
| 機種によって操作方法が違うので習熟しておくこと |
 |
| 隠したビーコンを探す |
 |
| やはり皆が目的地に集まる |
 |
| 無事に発見しました |
 |
| 雪庇を踏み抜く |
 |
| ふ〜しんど |
 |
| 踏み抜いた跡を利用してHZUの講義が始まる |
 |
| 指で押し雪層の感触を味わう、次に脇を掘って雪柱を作る |
 |
| 雪柱の破壊実験をして弱層を確認する |
 |
| 弱層(切断面)は斜めになっている、これが雪洞を掘る時のポイントになる |
 |
| 自分で体験してみないと身に付かない |
 |
| 雪の性質が分かったところで雪洞の作り方に話が及ぶ |
 |
| 気がつくと日本海が見えていた |
 |
| 広大な開拓地が今は放棄されている |
 |
| 下山を開始する |
 |
| 訓練地を振り返る |
 |
| バンガローの群れ |
 |
| 今回お世話になった鳥海山荘 |
 |























