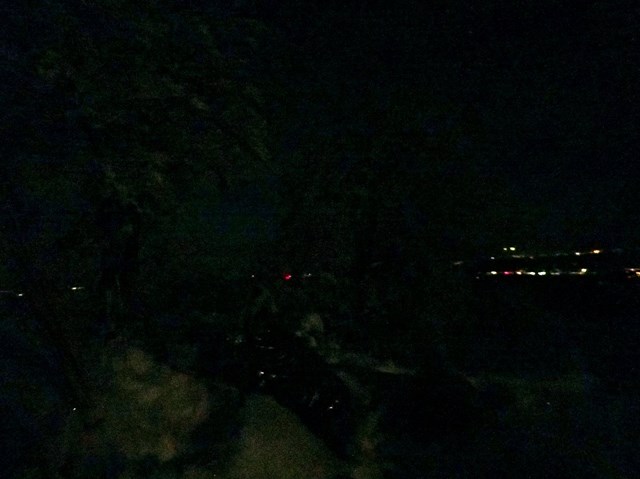登山者情報1,931号
【2015年12月27〜31日/権内尾根〜杁差岳/清水洋樹・加賀谷亮 調査】
一昨年(登山者情報1740号)昨年(同1848号)に引き続き、本年も大石から杁差岳を目指して入山した。昨年は豪雪、本年は極端な寡雪で状況がまったく異なり新雪の乗った斜面は極めて不安定であることが予想された。
今回は「ヒトココ(子機=発信専用)」なる位置発信機を携帯した。これは約3ヶ月の長時間探索電波発信と約1Kmにもわたる捜索範囲(親機=探査&発信)を実現した機器である。(インターネットで「ヒトココ」と検索すると出てくる。レンタルも行っている模様)
1日目:12/27(天候:雪時々曇り 風弱し)
【1日目行程】
早朝:東俣彫刻公園まで車両が入ったので、ここに荷物を置いて、大石ダムサイトに戻る。
7:37 大石ダムサイトに車両を置き出発(積雪無し)
8:05 東俣彫刻公園着・荷物を背負う(積雪無し)
9:10 一橋通過(積雪・3〜10cm程度)
9:40 二橋通過(積雪・〜15cm程度)
11:12 H631m雨量計跡通過
12:00 標高730m付近 幕営地着
【1日目概要】
・ 積雪は極端に少なく、終日つぼ足での行動となった。
・ 遠くでは風が木々を揺する轟音が聞こえているが、権内尾根は比較的穏やかだった。
・ 翌日は千本峰までで途中幕営適地が無いので本日は早めに行動を打ち切った。(カモス峰も地形的には良いが風が強い)
・ 夜は軽く積雪があった程度(昼から朝まで合計約20cm位)で比較的穏やかであった。
2日目:12/28(天候:雪 風速〜15m程度)
【2日目行程】
9:00 幕営地(H730m付近)出発
9:18 カモス峰 H847m 通過
10:55 権内峰・小休止
13時頃 千本峰の先H1160M幕営地
【2日目概要】
・ カモス峰の標識は雪が強風に飛ばされ埋もれていなかった。
・ カモス峰のすぐ先で熊の足跡を発見。暖冬の折まだ動いている模様。
・ 権内への登りに掛かると地形は一変して険しくなる。
・ 権内峰への直登は出来ず、北西の斜面(オープンバーン:雪崩注意)を廻り込んで西北西の尾根に乗り山頂へ出た。
・ 鞍部H1042mの先まで雪庇の発達した痩せ尾根で注意が必要
・ 終日スノーシューにて行動
・ さすがにカモス峰から先は厳しいラッセルを強いられた。
・ 夜は軽く積雪があった程度(昼から朝まで合計約30cm位)で幕営地は穏やかであったが終始風音が聞こえていた。
3日目:12/29 初回アタック (天候:雪 風速10〜前杁差岳付近で瞬間30m程度)
【3日目行程】
7:23 幕営地H1160M出発
9:30頃 前杁差岳三角点(本日はここまで)
10:30頃 幕営地H1160M帰着
【3日目概要】
・ 標高1200m付近までは厳しいラッセル。新雪と旧雪との境界が滑りペースが上がらない。
・ 標高1230m付近からは地形判然とせず、のっぺりとした山稜で旗竿ベタ打ちとなる。
・ 標高1230m付近から上は風衝地帯で潅木が枝先を覗かせる。この辺りからクラストが顕著になる。
・ 前杁差岳の標識がかろうじて頭を覗かせていた。
・ 前杁差岳標識の手前よりほぼホワイトアウト・三角点にて本日は撤退とする。
4日目:12/30 アタック登頂 (天候:雪 風速10〜前杁差岳付近で瞬間30m程度)
【4日目行程】
7:30頃 幕営地H1160M出発
9時頃 約30分間天候回復を待ちツエルトにて途中待機
10:03 前杁差岳三角点通過(往路)
10:49 二つ池付近通過
11:07 杁差岳山頂
11:46 前杁差岳三角点通過(帰路)
12:40 幕営地H1160M帰着
【4日目概要】
・ 風は強いが、昼前から天候回復との予報に期待し前杁差岳への途中でツエルト待機するも、一向に回復せず。
・ 前杁差岳から先、時折微かに視界が開けるので、清水=GPS 加賀谷=高度計+コンパス+地図 のシステムで山頂を目指す。
・ 標高1580m付近から地形判然とせず、旗竿のピッチを狭くする。
・ 終日スノーシューによる行動。前杁差岳から先は部分的にラッセルも大半はクラスト。
・ 帰路はホワイトアウトの度合いが強まり、2名で間隔をあけて、常に1本の旗竿をキープして行動する。
・ 前杁差岳付近が最も風が強かった。
・ 3年越の杁差岳山頂であったが、強風のため2分程度の滞在にて帰路についた。
・ テント帰着後は、翌日下山に備え早めに祝杯をあげ7時頃には就寝したが、10時頃ふと起きると、星空と夜景、満月に照らされた前杁差岳差の神々しい姿を目にする事が出来た。結局翌朝は視界は無く、天候が回復したのはこの一時だけだった。
5日目:12/31 下山 (天候:雪〜下部は雨 風速〜10m程度)
【5日目行程】
8:05 幕営地H1160M出発
8:14 千本峰通過
9:09 権内峰通過
9:42 カモス峰通過
11:07 二橋通過
12:06 一橋通過
14:04 東俣彫刻公園
14:49 大石ダムサイト着
【5日目概要】
・ H631m雨量計跡の下部急坂はロープを出した。
・ H631m雨量計跡まではスノーシュー、これより下部はカンジキにて行動。
・ カモス峰の下H810mで権六峰への尾根を分ける箇所は要注意
・ 1〜2橋間のトラバースは雪が載り通行不能、H445のピーク近くに登り尾根を下った。
・ 雪が全く無かった林道は30cm程度の積雪に覆われていた。(スノーシューにて)
・ 帰路、大石集落にて、情報提供頂いた関川山の会の方に感謝の挨拶をした後、上関共同浴場にて本年最後にして最高の湯を楽しんだ。
【総括】
・ 今回は下部アプローチでは寡雪に助けられ、大いに体力を温存する事が出来たとともに、林道でのリスクから免れる事が出来た。
・ 寡雪とは言え、カモス峰付近からは例年と変わらぬ激しいラッセルを強いられた。
・ 一昨年、昨年に続く3回目であり、前回に前杁差岳差に達していたため今回は精神的余裕があった。
言うまでも無いことだが、回数を重ねて地形を把握する事は重要である。
・ 前2回の経験で、幕営適地を把握していたことも大きく、今回は夜間除雪を強いられる事も無く快適であった。
・ GPSのコンパスはふらついて当てにならない、やはりコンパスの威力は絶大である。
| 今回携帯した「ヒトココ発信機」 |
 |
| 雪の全く無いダムサイトを出発 |
 |
| 一橋を渡る(先行するのは地元のマタギ衆) |
 |
| 去年の一橋 |
 |
| 二橋へのトラバース |
 |
| 雪の無い二橋を渡る |
 |
| 雨量計への急登(つぼ足) |
 |
| 雨量計の峰が見える(雪は少ない) |
 |
| 雨量計の峰からカモス峰と権内峰(奥) |
 |
| カモス峰への登り(スノーシュー) |
 |
| カモス峰の標識(埋まっていなかった) |
 |
| 熊の足跡(カモス峰の先にて) |
 |
| 権内峰へのラッセル |
 |
| 権内峰直下のトラバース(夏道外) |
 |
| 権内峰付近より千本峰方面 |
 |
| 霧氷が美しい |
 |
| 権内峰を振り返る |
 |
| 千本峰への急登&激しいラッセル |
 |
| 東側は絶壁 |
 |
| テント場を出発(29日初回アタック) |
 |
| 旗竿デポを回収 |
 |
| 前杁差岳への激しいラッセルと格闘 |
 |
| 千本峰方面を振り返る |
 |
| 前杁差岳へ到着(29日・本日は撤退) |
 |
| 千本峰テン場への帰路(右手の雪庇に警戒) |
 |
| 再び前杁差岳へ向かうラッセル(30日・再アタック) |
 |
| 東側はこの通りの絶壁 |
 |
| 前杁差岳へはクラストした急登.が続く |
 |
| 杁差岳山頂にて(清水) |
 |
| 杁差岳山頂にて(加賀谷) |
 |
| 杁差岳山頂にて(遊びで2名合成写真) |
 |
| ホワイトアウトの帰路 |
 |
| 前杁差岳から下降すると視界が回復してきた |
 |
| 着氷したブナが美しい |
 |
| 夜ふと起きると夜景と星空が広がる |
 |
| 見にくいがテン場からの前杁差岳 |
 |
| 関川村方面の夜景も |
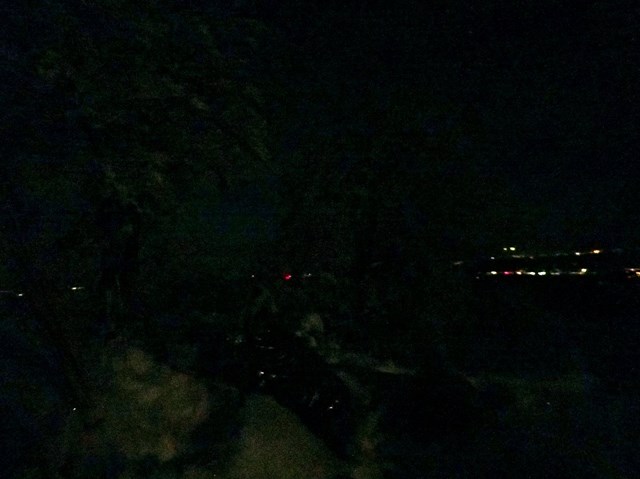 |
| 朝のテン場より(31日・左奥に雨量小屋のアンテナ?避雷針?) |
 |
| 着氷した木々 |
 |
| 雪庇が切れている箇所も |
 |
| 千本峰に登り返して一息 |
 |
| 千本峰の雨量小屋 |
 |
| 千本峰からの下り(昨年へつった箇所) |
 |
| 昨年の状況(雪壁を切ってへつった) |
 |
| 権内峰へ向かう |
 |
| 権内峰より千本峰方面を振り返る |
 |
| カモス峰付近のラッセル |
 |
| 権内峰直下のトラバース(帰路) |
 |
| 雨量計跡からの下降(ロープを出した) |
 |
| 積雪した二橋を渡る |
 |
| 積雪した1〜2橋間のトラバース(通行不可にて尾根通し) |
 |
| 積雪した1橋を渡る |
 |
| 昨年の林道核心部(アイゼン使用箇所) |
 |
| 昨年の状況(上部からの水滴で氷化していた) |
 |
| 雪に覆われた東俣彫刻公園 |
 |
| ダムサイトへ帰着 |
 |
おわり