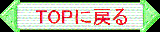
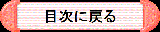 |
登山者情報第2,401号
|
【2024年10月29日~30日/三ツ石山オーバーユース検討会/草刈広一他】
|
岩手県三ツ石山オーバーユース対策現地検討会が開催され、長年近自然工法を実践してきたNPO法人飯豊朝日を愛する会が協力することになりました。会から私の他、初日は2人、2日目は1人の応援部隊が駆けつけてくれ、主催の環境省や森林管理署(盛岡、北部)、岩手県、雫石町、八幡平市、実際に保全作業を行っているガイドなど述べ30人ほどが試験的な保全作業に加わり、たいへん歩きやすくなりました。
|
 |
初日の作業の前に飯豊山地での保全の事例や近自然工法について説明(網張温泉)
|
 |
初日は網張温泉側から三ツ石山荘まで行き、降りながら作業を行う。
|
 |
立ち枯れ木を伐採して、みんなで運ぶ
|
 |
切り出した立ち枯れ木の配置を検討する
|
 |
完成してふりかえり
|
 |
参加者のパワーで見違えりました。
まず登山道脇のチシマザサをみんなで刈って麻紐で束ね敷き詰め暗渠にして、登山道脇にあり倒れる危険のある立ち枯れたアオモリトドマツを利用して、くの字、逆くの字にカスガイでつなぎ止め、それぞれのコーナーにササの落ち葉などを敷き詰めて完成。
|
 |
2日目は松川温泉ルートでまた同じような場所で、昨日より幅が広く、平らなこともあり、チシマザサも束を横に敷き詰めつことに
|
 |
泥上の箇所は多いが、今日はここを保全することに。
私は松川温泉側から山スキーで登っただけで、荒れている様子を見るのは始めてだし、平坦な場所での作業計ケインはなく、かなり戸惑う。
|
 |
2日目の作業前に、近自然工法の歴史や意義について説明する須藤さん
|
 |
まず束ねたチシマザサを横にしいてから立ち枯れ木を組んでいく
|
 |
立ち枯れ木が組み終えたら、落ち葉などを集め敷き詰める
|
 |
その結果、暗渠のササの束はみえなくなる
|
 |
細部の段差調整
|
 |
みんな泥まみれになりますが作業に夢中
|
 |
細い枝だけでなくササを刈るのにもハンディなバッテリー式チェーンソーが大活躍
|
 |
作業してたらハコネサンショウウオを発見
|
 |
 |
そして完成
|
 |
振り返り
|
 |
おわり
|